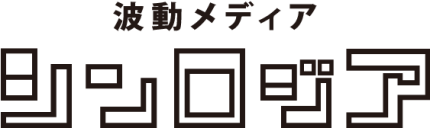さくら開花の便りが始まり車を走らせると、田舎の山々にもうっすらと淡いピンクの山桜が見え始めました。昼間の太陽の元では、満開へと花びらが開きますが、少し冷え込む夕刻になりますと、何故か淋しい空気を醸しだすと感じるのは何故でしょうか。よく桜と言うのは樹木の霊性を感じさせる代名詞のように言われますが、まさにこの国の土地と民と共に生きている生命でしょう。
この国を愛す、地域を愛す、生命を愛す魂の伝説があります。戦後、国家発展のために電源開発がすすめられ、ダムを作る事で水力発電事業が各地で始まっていました。その一つに、岐阜県にある御母衣(みぼろ)ダムプロジェクトがありました。白川郷で有名な白川村一部と壮川村の三分の一が湖底へと沈む計画案が昭和二十七年十月十八日に発表をされ、当時地元の村民(約1200人)が反対を旨に「御母衣ダム絶対反対期成同盟死守会」と名を打ち立ち上がりました。そして、電源開発初代総裁の高碕達之介氏との交渉が始まりました。動植物愛好家の政治家であった高碕氏は、細やかな情の持ち主で、地元村民との交渉が始まりました。ダム建設へ向けて、七年の交渉後地元村民と合意がなされた時、湖底へ沈む二つのお寺に樹齢四百五十余年の桜の巨木の二本を目にして、国作りと言う大きな仕事の前に、父祖伝来の故郷を捨てた方々の犠牲が生かされる為にも、この二本の桜の巨木とお寺の移植・移転を決意し、当時日本随一の桜博士と言われていた笹部新太郎氏に力を借りて行われました。そして、笹部氏や住職はじめ大勢の祈りの中、昭和37年の春活着の見込みが出始め、記念日に集う元村民はその巨木の周りで心尽きせぬ感無量の時を迎えたそうです。その桜のもとに高碕氏の歌碑が納められています。
「ふるさとは 湖底(みなそこ)となりつ うつし来し
この老桜 咲けとこしへに」
そして、ふるさとという言葉に最もふさわしい存在が桜であり、荘川桜と名がつけられ今では「死守会」から「ふるさとを守る会」へと発展して、元村民ならず桜愛好家や大勢の観光客の訪問を受けています。
更にこれに続く伝説があります。この国には「桜街道」と名がつく名所が数々あります。そして、この荘川桜に関する「桜街道」が国道156線にあたります。日本を南北に縦断する名古屋から白川郷を経由して金沢まで、266キロを繋ぐバス路線です。昭和40年頃、壮川桜が再び花開した時に花見に来ていた老婦が桜の幹に涙しながら抱きついているのを目撃し、それにより感動をした旧国鉄バスの車掌であられた佐藤良二氏が「太平洋と日本海を30万本の桜で結ぶ」と言う夢を抱き、実現に向け動いたお話です。約10年と言う月日の中で、職務の合間に苗木を作り、路線沿いに移植をし、約2000本の所でお亡くなりになったそうですが、その後も引き続き意志を継ぐ方々により移植されていたとのことです。
この度の話は桜でありますが、この植物を通して魂の響き合いにより紡がれ、桜街道と言う形が現れ、毎年のように日本人のこころを掴んで止まないのが桜という波動でしょう。この桜の木の波動で、春と言う生活の始まりを認識するのが日本人ではないでしょうか。歴史的場面でもよく桜は登場します。始まりだけでなく、散り際の良さが美化表現され、ヒトの一生もこうありたいという願望が内在しています。伝説のお話のように、魂が揺さぶられることに出会うと、たった1人であっても成すべきことが遂行出きるというのと、そのことが必要な道なら、続く者が現れ繋がり紡がれていく世界であることを、この桜の話は教えてくれていると考えます。
その魂の根底には、遺伝子的に連綿と繋がっている「愛」ではないでしょうか。自然を愛し、ヒトを愛し、地域を愛し、やがては国を、地球を愛することが日本人の本来の本質であると考えます。今、この「愛」の響き合いを願ってやみません。