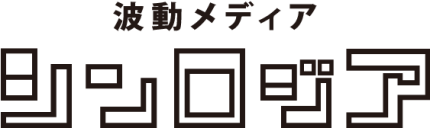節分も過ぎ三寒四温を楽しみにしている中、毎週のように寒波到来にて、今年は雪を何回もみせて頂いています。そして、その雪に喜こぶのは子どもたちです。あちらこちらの家の庭には、雪だるまが登場して、その顔は作り手の子どもの顔をしているのが、とても楽しいものです。また雪は、子どもからしたら、包み支えてくれるものの様に感じているようです。一面真っ白な雪の絨毯に、長くつの足跡が、猫の足跡が並ぶのは、一種の芸術にも見えます。
また、雪の下の野草や野菜は太陽による雪解けと共に、何事も無かったかのように凛とした姿を見せてくれます。20センチの雪に覆われても、生きているのです。やがて雪解けした畑には、雉らしい姿が見えるようになりました。それも成長期らしき大きさの雉で、体の赤や濃紺、緑色のカラフルな色は見受けられず、地味な色合いは、もしかしたらメスかもしれませんが、畑の草の下をついばんでいます。それも一羽でです。雉の世界は、父親は子育てをしないそうで、それは母親の仕事らしいです。一羽で独り立ちのじきなのでしょうか。どこかで母雉は見ているのでしょうか。よく、昔話の中の鬼退治に雉が登場し勇猛果敢な鳥と言われますが、メスへの求愛に関しては「けんもほろろ」と言う言葉があるように、女性には弱い所もあるようです。それでも、他のオスや天敵(アオダイショウレベルでも)の前ではなかなか勇ましい生き物の様です。そして、最大の特徴はメスの母性愛の強さだそうです。その情の深さの表現として「焼け野の雉夜の鶴」いう、巣を焼かれた際わが身に変えて子を救おうとするメスの姿を現しているそうです。また、鶴も凍えるヒナを羽で覆い夜の寒さから守るそうで、情の表現とされています。勇猛果敢な父と母性愛の強い母とによる家族作りは、今思えば日本の象徴とされても納得がいくものです。
さて巷では、学生の受験期間もそろそろ終盤のようです。夕刻、最寄りの駅にいる学生さんたちの姿を見ていると、緊張感も減り笑顔の多い仲間同士の光景から、希望が伺える雰囲気を感じます。そろそろ新学期に向けて、世の中の動きが忙しくなるようです。ところで、最近では受験先の合格発表を両親が同行する姿がニュースに映りますが、自身を振り返りますと子供の合格発表会場へは出向いたことが無いように記憶します。
第一子は就職氷河期前半にあたり、四年後には世の中も変わり就職が楽になっているとの予測から、時間稼ぎとして大学進学を担任から進められ、母親としては怒りが湧いてきたのを思い出します。しかし、高卒出の父親から見たら縦社会の組織の中での辛さを知っている為、本人が希望とのことならと進学を承認しました。自身の中では、何か煮え切らないものがふつふつと湧き、異文化交流の夫婦の不協和の種が一つ増えたものでした。第二子以降になると女子という事もあり、いずれ結婚と言う事になる為今のうちに好きなようにという選択肢が特徴だったように思います。ですから、その後受験の申請も発表も子ども自身で進めたように記憶します。
では、このふつふつと湧き出るものに向き合うと、夫婦の其々の生きてきた成長過程の違いに気づきました。子どもが幼稚園や小学校の間は、親の子育ての労働割合が肉体労働がほとんどだったので夫婦共協力できますが、中学や高校生ともなると精神労働が伴います。その精神労働においてそれぞれの経験や体験により意見相違と言うものが発生するのです。この精神労働は、生き方の課題にも繋がる為、夫婦の妥協点を見出すのに時間を要します。とは言っても、親の課題と子どもの課題は別なので、子ども自身に任せればよいものを、転ばぬ先の杖をつい出してしまいます。また、就職氷河期と言う言葉の持つエネルギーに恐怖心を抱き、更に時間稼ぎと言う言葉に、自身の中では煮え切らなくなっていたのでした。
社会へ出てゆくまでに、「自分は 今 なぜで生きているのか」「何をしたいのか」の思考時間の深さとそれに伴う経験により、社会へ出てからの生き方が色々になるのではないかと考えながらも、子どもの意志を尊重できない事へは当時の母親としての変な強さの内在に、後に苦しむことになりました。また近年では、尊敬する又は憧れる大人を見る、または出会う機会が少なくなりつつあるので、この時間稼ぎの中で出会う事を願いました。子どもは、親を通してサラーリーと言う仕組みで動いている社会を見ていますので、どうしても子ども自身が人生を安全圏や楽な方へ選びがちのようになります。その一つとして、自身の結婚もその安全圏の方向性での選択であったと思います。一人で生きてゆくというほどの覚悟が足りない事も恐怖心でもある事をも自覚していました。それが魂を売って生きるということの一つになる事を後に知りました。
そして、振り返れば自身の両親は、再度家庭を作り最後まで子育てをした父と、自分の気持ちを素直に通して、最後まで一人生き抜いた母のもとに生まれ、考えさせられることばかりです。もしかしたら、父性と母性の反転の家族の中に生まれたのかもしれないとか、この自身に内在している父性と母性について再考する今日この頃です。