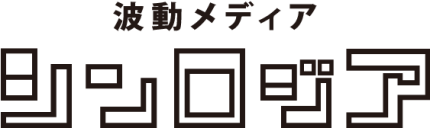大寒波の予報で昼頃から降り始めの雪は、夕刻には深々と積もる雪に変わり出しました。身体が慣れたと言え、今朝の-8度は久しぶりに身に沁みました。しかし、旭川での-15度の体験を思えば、まだ暖かいほうです。それにしても南北に長いこの国は、30度程の温度差が内在する不思議な国であります。畑の野菜は流石に凍っていますが、お料理にはまことに柔らかい美味しい味を出してくれます。耐え忍んだ味と言うのがこのようなものかもしれません。実は煮崩れせず、後味の清々しい気分は何とも言えず、思わず涙が出そうなお野菜なのです。
さて、年が明け目まぐるしいニュースの流れの中に、大問題の内容が出ました。厚生労働省より「2024年自殺者」の統計です。全体では一昨年よりは減っている中で、子ども自殺数が過去最大になっているという事です。こども家庭庁では7兆円の予算が組まれていると報じられました。ネット上では、子供食堂へもっと予算をとの声が結構上がっていました。この子供食堂の発足当時は、こどもが施しを受ける趣旨に疑問を思い、この食堂が発生すること事態が、国の恥ではないかと考えたことがありました。今では、こどもと一緒に作り家族と共に食事が出来るそうですが、その発足当時は、施しを受ける食堂が多かったと記憶しています。本来は施しを受けるのではなく、子供の自立心や術を身につける機会が必要と考え、公民館サイドに相談をして「わたしもぼくも家(おうち)ご飯」と題して、料理教室をコロナ禍になるまで続けました。
その「お家ごはん」と言うのは、小学生を対象に「自分の為に作る」、「家族の為に作る」を主軸に、初回はメニューの提示をしましたが、やがてグループごとにメニューを組み立て、買い物までします。年齢は1年生から6年生まで混合グループを作り、年を重ねて中学へ進んだ生徒はやがてスタッフ見習いになりました。スタッフは、子育て後半から子育てが終わった世代で構成され、「ただ見守るだけ」を指針にします。これが中々難しいのですが、会を重ねるごとにスタッフも子育ての反省を含め、自分磨きが始まりました。年齢が近いのかこどもの気持ちがよくわかる中学生では、大人スタッフよりこどもへの接し方が上手であることが判明したものでした。料理が出来上がる午後六時には家族の方に来ていただき会食をします。最初はお迎えかねての母親ときょうだいでしたが、やがて忙しい父親も仕事を切り上げ六時には参加する父親が増えました。自営業の方が多いのですが、サラリーマンの父親もやがて早仕舞いをして会食をするようになりました。更に祖父母も参加という大家族の会食となり出しました。
お料理と言うのは、総合学習と何時も思っていましたので、学校へ行けなくても十分基礎学習へは繋がります。メニューは図書棚の料理本を参考にしたり、分からなことはスタッフと一緒にネットで調べたり大人の知恵を借ります。会食の人数が増えますと、こどもは張り切り、数字の計算だけでなく、予算と向き合い見切り品の選択まで大人の背中をよく見ていることが伺えます。スーパーでは、計算係、カート押し担当、商品の選択係、店員への問い合わせや交渉役など、自然に役割をこなす姿にびっくりしたものでした。決して、大人が手出しをしなくとも成立してゆく事がよくわかりました。本当に見守るだけで良いという事です。ことがおきれば、必ず駆け付け対処を誰かがするということも分かりました。見守られていると、こどもは子供同士で解決するという事に気が付きました。そして、盛り付けもあっさり型から凝るグループまで色々です。グループごとにメニューが違い、こどもは別に関心が無くても、親の目がキラキラと比較を始めるなど面白いです。やがて、料理のおすそ分けをしたり、交換が始まりました。そして、この日を楽しみに、一番くつろいで満足顔の父親の姿が印象的でした。最後は、全員で食器洗いから片付までをします。ここではご家庭での様子がよく見えます。怒るようにいう親やママ友談義に花が咲きます。最後まで丁寧に隅々まで気を配り仕舞をしてくださるのは父親です。仕事場もこの姿勢で、家族を守っているのかと思うかと頭が下がる思いでした。最後は、家族ごとに帰宅をしたり、再び職場に戻る父もいます。それでも良いと思います。夕食を家族で食せる事の方が、夜遅く帰宅するより、父親の仕事姿が子どもにとっては逞しく見え嬉しいそうに見えました。昔、オーストラリアの留学生から聞いたのは、やはり夕食は家族全員でするそうです。そして、再び職場に戻るという職種もあり、当たり前な生活スタイルと聞きました。
また、仕事上親御さんと一緒に会食できない子供さんもおり、親のお迎えが遅いのも常連でした。この場合、公民館職員の方が連絡をして下さります。また、スタッフとの反省会で気になる子供さんへは、時々館の職員さんが連絡を取り、対応をしてもらいました。参加したくもどうしても家庭の複雑事情で言い出せない子供さんは、親の承諾交渉を館の職員が担当をして下さったりと色々ありましたが、こどもはとにかく食べる事、何においても作る事に関心が多く、やりたいのです。自分の命を保つことは本能です。その食の作る術を身につけていれば、その上で何事があっても生きてゆける方法の一つとして確信をしています。そして、見守る事の大切さが子供の心を放しません。心に何かを抱えている子供さんは、やがてスタッフにポツリポツリと話し始めます。時間は掛かりますが、この心の声を見逃さないことが、大人の関わりの大切さと考えます。無関心社会と言われる今、見守る大人が少なくなりつつありますが、自然界は常に人間と共に生きています。卵が先か鶏が先かでは無いですが、「親塾」も必要と考えた事がありましたが、教育の転換点がもしかしたら、自然界のしっぺ返しから始まるのかもしれないと最近思い始めました。自然界は必ず自然権を実行すると聞きます。今、外気温が下がり続け-5度ですが、3度しかない台所ではパンの菌が何事も無いかのように粛々と膨らんでいます。何があっても生き続ける事を、自然の中で学ぶ教育がこの社会に必要では無いでしょうか。そして、自律するまでを支えるのがヒトであり大人の役割と再認識しました。命を見過ごした大人の一人として、審判を希求します。